防災は日頃の備えと健康から
防災健康サポーターは
誰でも受講OK
オンラインで学べる
災害時、避難生活が長期化すると
健康への被害が拡大します。
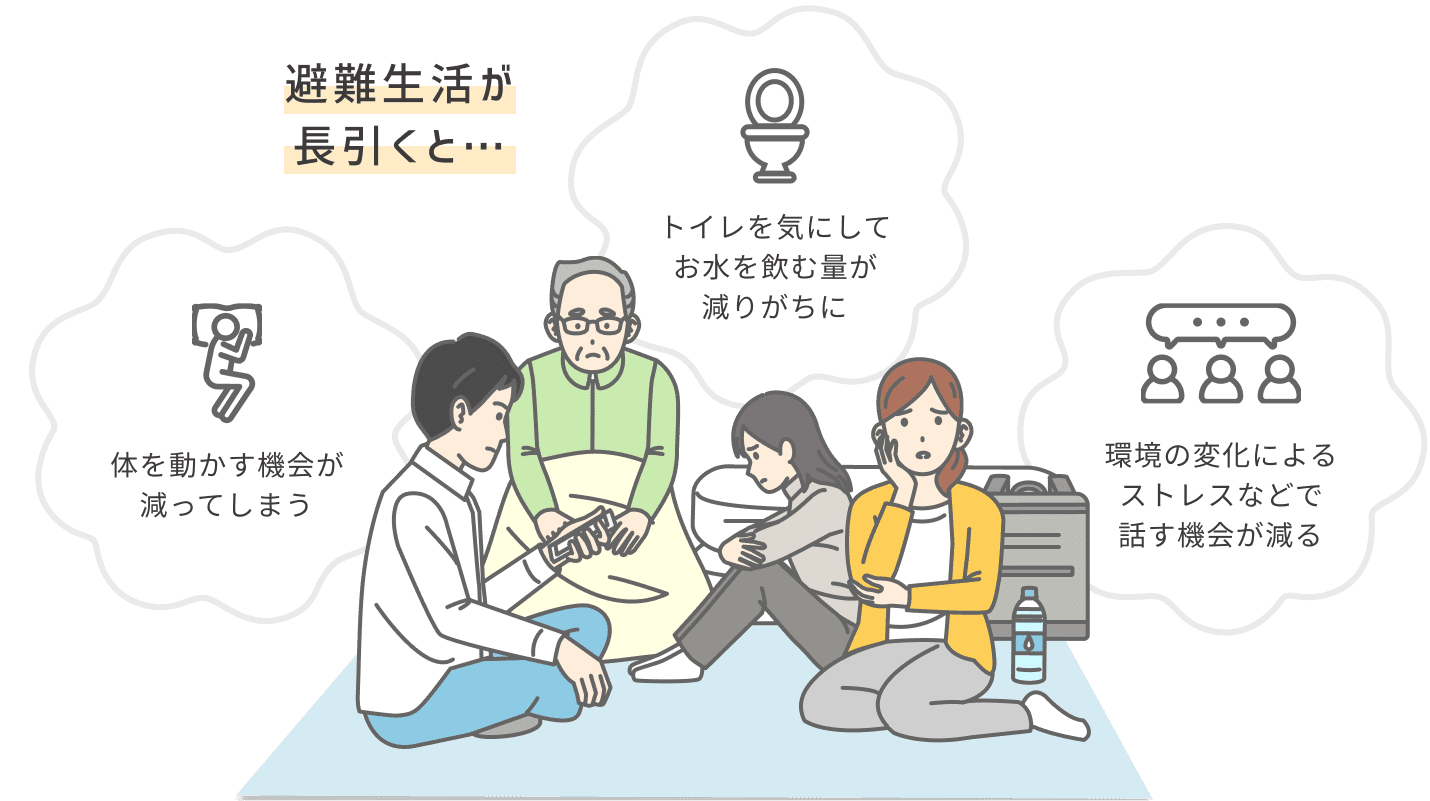
とくに高齢者は、体を動かす機会が減ることで心身機能が低下し
「ロコモティブシンドローム※」「認知症」のリスクが高まります。
※ロコモティブシンドローム(運動器症候群)
加齢や生活習慣によって骨・関節・筋肉の機能が低下し、歩行障害が起こること。
健康に被害が出る前に、予防が大切です。
健康二次被害を防ぐために、意識したい3つのポイント

適度な運動
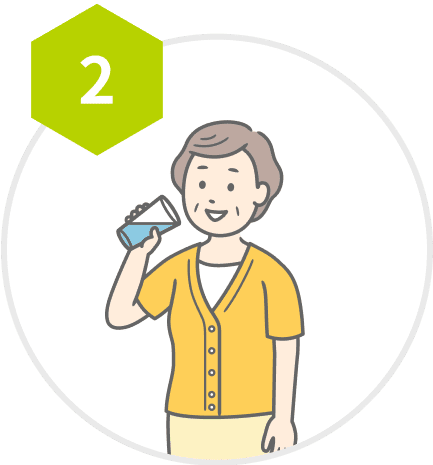
こまめな水分摂取

人とのコミュニケーション
その対策のために生まれたのが、
防災健康サポートプログラムです。
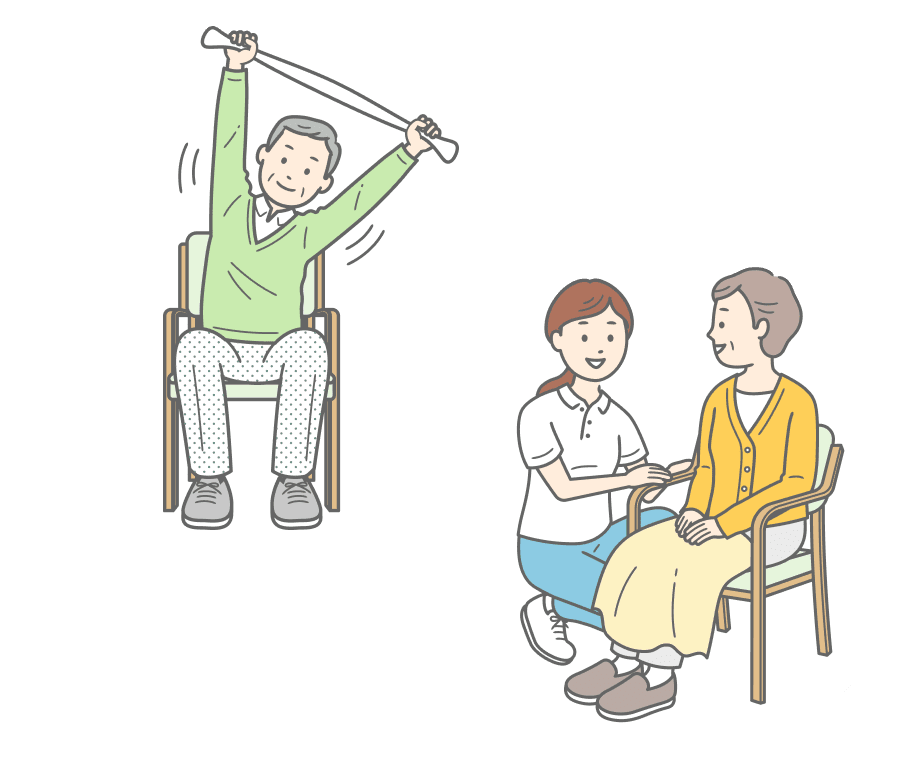
日頃の備えが、
自分や家族を守る力に
- いざという時に備えられる
- 大切な人を支えられる
- 地域をつなぐ力になる
動画で学んでみよう!
動かない(座りっぱなし)のリスク
災害時に備える太もも・お尻の運動
スクワットでぼうさい体操
自分の健康を守りたい方
もしもの避難生活でも健康に過ごせるように、
健康二次被害を防ぐ方法をやさしく学べます。
家族や地域住民の健康を支えたい方
避難生活では「声かけ・見守り・健康の気づき」が大切です。
防災健康サポーターは、専門知識がなくてもオンラインで学び、地域で活かせる新しい健康支援のかたちです。
防災・福祉・健康担当の自治体職員の皆さまへ
災害時の健康二次被害を防ぐには、地域の担い手育成がカギです。
自治体での活用方法、研修ツール、導入事例をご紹介します。
監修者紹介

町田 修一先生
順天堂大学大学院
スポーツ健康科学研究科
教授
災害時こそ「動くこと」を意識し、ご自身やご家族、地域の皆さまの健康を守りましょう。無理のない範囲で体を動かし、心と体の機能を保つことが大切です。本プログラムが、大切な方々の健康を支える一助となれば幸いです。
推薦者紹介

松尾 一郎先生
東京大学大学院
情報学環総合防災情報研究センター
客員教授
熊本地震や能登半島地震では、直接死よりも災害関連死が増加しています。 この災害関連死の解消には、被災者自らが健康被害防止に取り組めるよう「防災健康サポートプログラム」を命を守る備えとして頂ければ幸いです。
協力

福島県いわき市
