体を動かさないと、どんなことが起こる?
普段の生活では気づかないうちに、意外とたくさん動いています。
避難生活では、「動かないこと」が思った以上に健康に影響します。
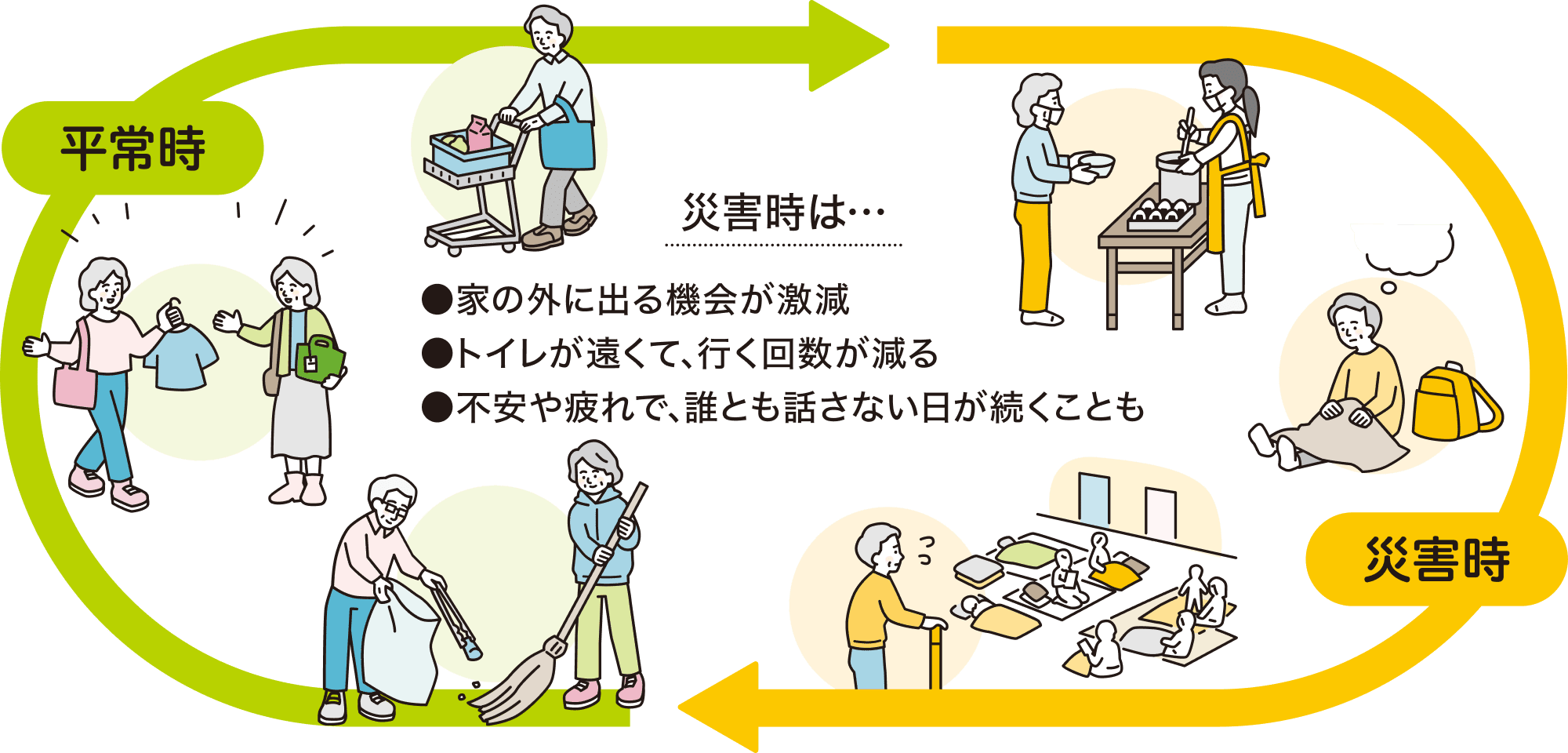
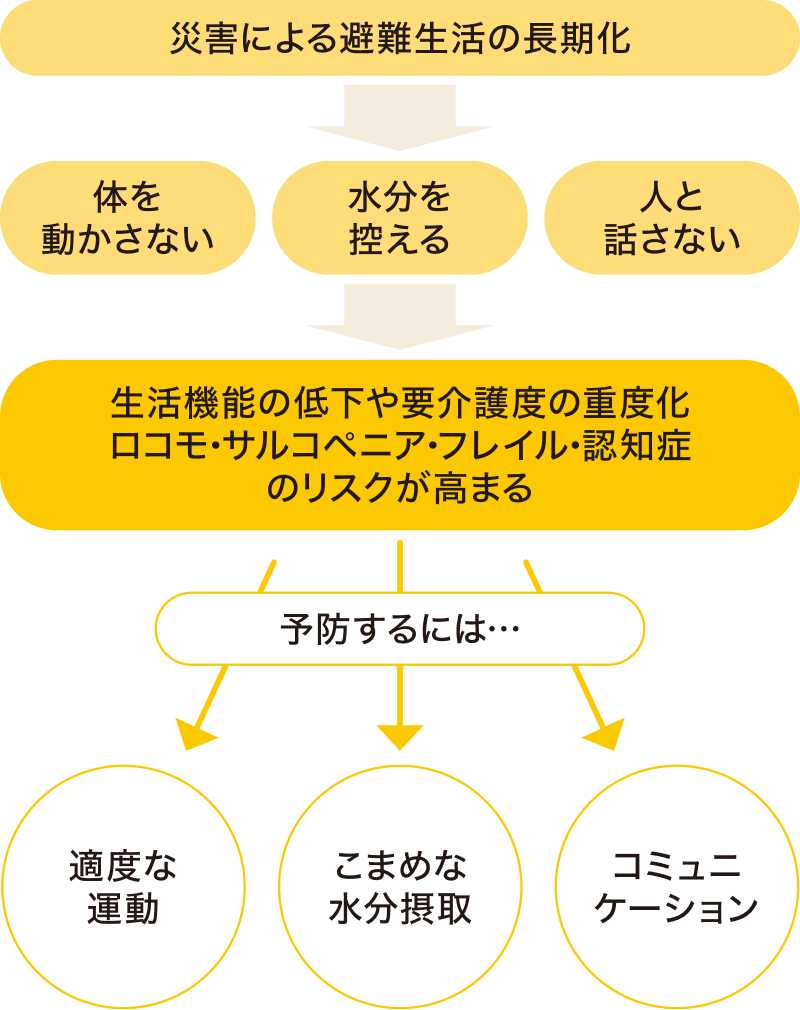
“動かない”は
要支援・要介護の要因に
体を動かさない生活が続くと、骨・関節・筋肉が徐々に衰えていき、筋力の低下、関節の痛み、歩行障害、さらには認知機能の低下といったリスクが高まります。
また、水分不足による脱水や、人とのコミュニケーション不足も、健康への悪影響を及ぼす要因となります。
健康二次被害を防ぐために、日頃のちょっとした意識と、周りとのつながりが鍵となります。
知っておきたい用語
メタボ(メタボリックシンドローム)
内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態。
サルコペニア
加齢により筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下した状態。日常生活にも支障をきたす。
ロコモ(ロコモティブシンドローム、運動器症候群)
加齢や生活習慣によって骨・関節・筋肉の機能が低下し、歩行障害が起こること。
フレイル
加齢によって心身が衰え、回復力が低下した健康と要介護の間の虚弱な状態。
健康二次被害を防ぐためのポイント
避難生活では、体を動かす機会がぐっと減ってしまいます。
そのまま何日も座りっぱなしや寝たきりのような状態が続くと、筋肉が弱りやすくなり、
歩くのがつらくなったり、転びやすくなったりすることがあります。
災害時に鍛えるべきは、
「太もも」と「お腹」の筋肉。
- 太ももの筋肉
- 立ち上がったり、歩いたり、踏ん張ったりするときに欠かせない筋肉です
- お腹の筋肉
- 体のバランスを保つのに重要で、背中や腰の負担を減らす働きもあります
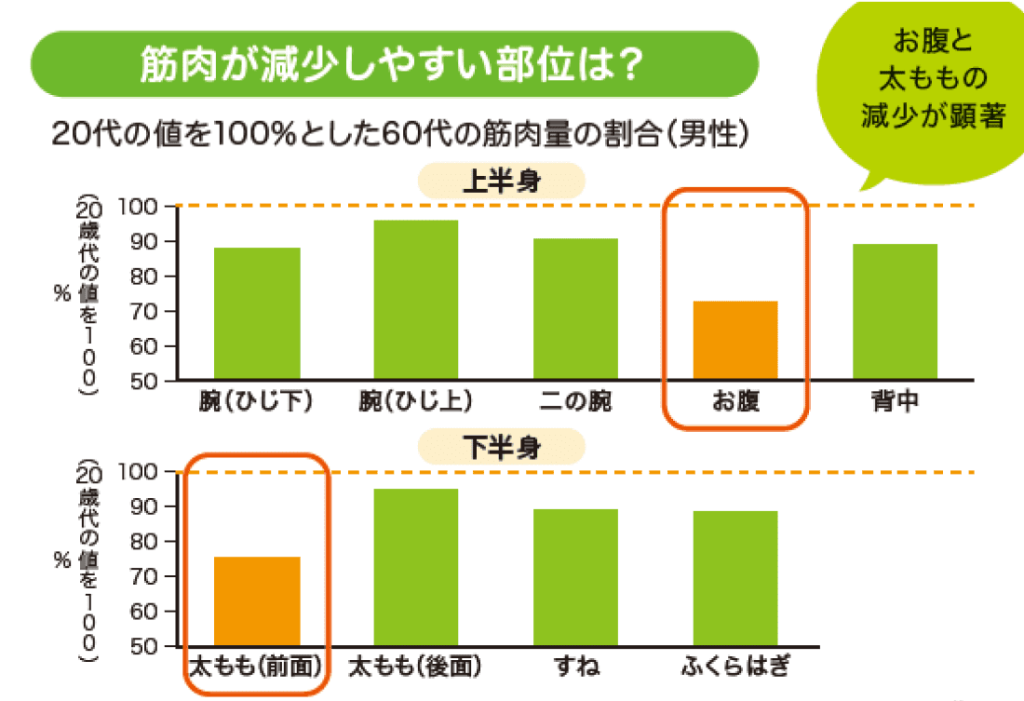
筋肉を守るためにも
水分補給を忘れずに
筋肉の約7割は水分でできています。水分が足りないと、栄養や酸素がうまく届かず、筋力が落ちる原因にもなります。高齢の方は、のどの渇きを感じにくくなるため、意識してこまめにお水を飲むことが大切です。
「声をかける」だけでも
心と体の健康を守れます
避難生活では、人と話す機会が減りがちです。
あいさつやちょっとした会話があるだけで、気持ちが落ち着き、脳への刺激にもなります。「こんにちは」「大丈夫ですか?」のひと言が、心と体の支えになります。
日頃からできる“体の備え”
避難所などの限られたスペースでも、
ちょっとした意識と動きで筋肉を守ることができます。
無理なく少しずつ毎日続けてみましょう。
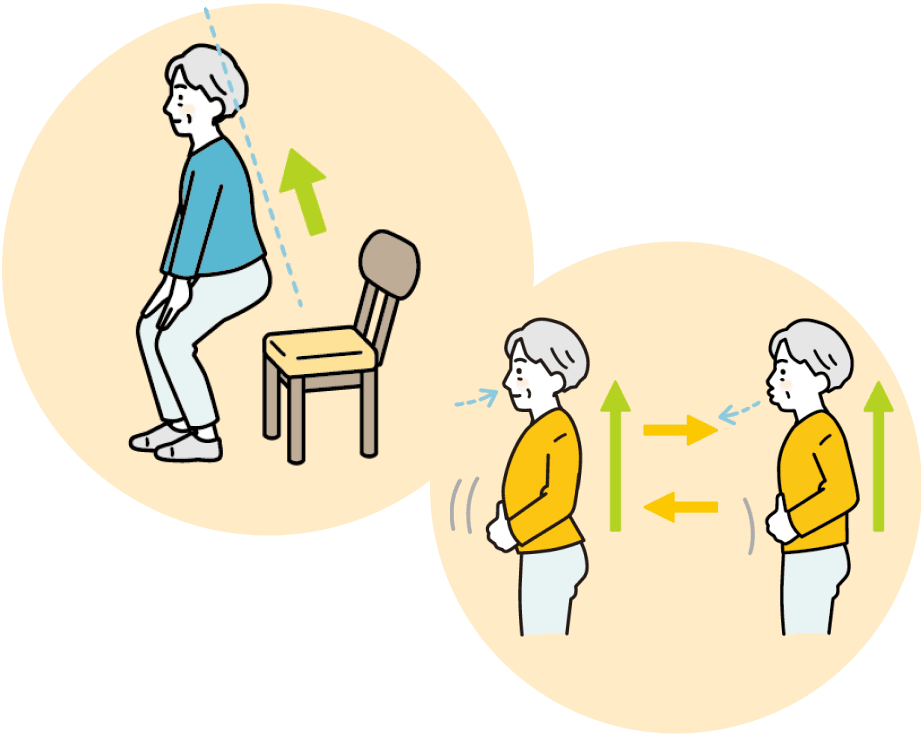
たとえば…
- 長時間座っていると感じたら
定期的に立ち上がる - 深呼吸しながら
お腹をへこませる
日頃からできる“体の備え”
3つのポイント
- 朝夕1回ずつ
- 呼吸を止めずに
- 痛みのない範囲で
今日からできる!1分かんたん体操
すきま時間に1分だけ!簡単にできる体操を紹介します。
体をゆるめてスッキリ!腰痛ケア
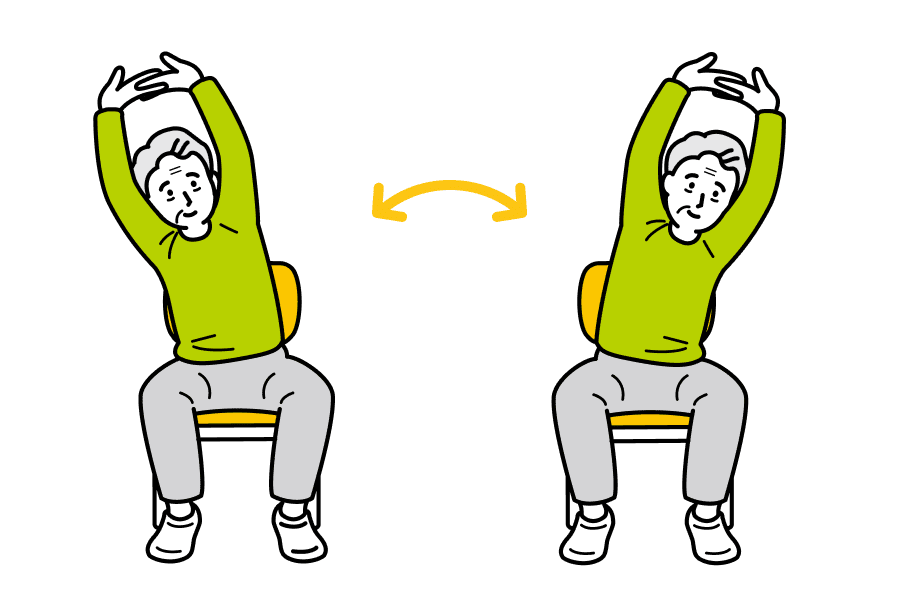
血行不良や筋肉が硬くなると、痛みを感じやすくなります。こまめに体を動かしてリフレッシュしましょう。
動き方
手を頭の上でくみ、 体を左右にゆっくり倒す
目安
左右10秒ずつキープ
ポイント
体を前後や斜めに倒すと腰回り全体を伸ばすことができます
動けるからだ作り!筋力アップエクササイズ
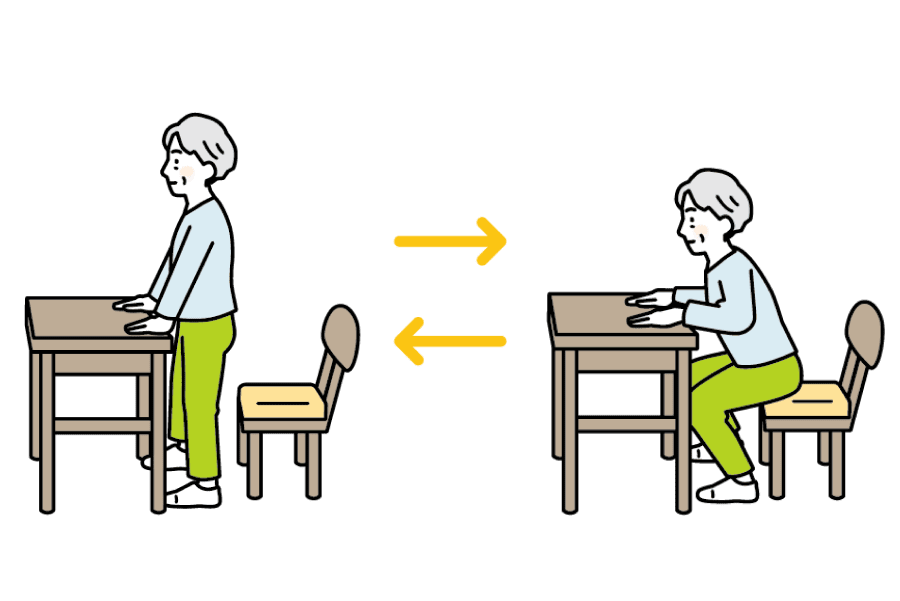
太ももとお腹を使うスクワット。継続することで、いつまでも自分の足で歩き続けることが目指せます。
動き方
- 脚を腰幅にひらく
- 机等の支えに手を添え、
立ち・座りを繰り返す
目安
3秒で立ち、3秒で座るペースで10回
ポイント
椅子から少しお尻を浮かせるところでキープすると、さらに効果的!